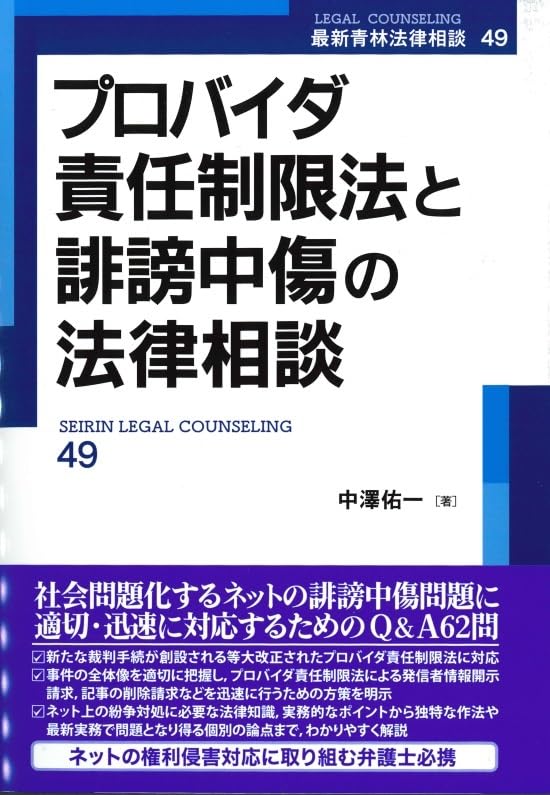「Law & Technology」第66号(民事法研究会 2015年12月)に『近時のインターネットをめぐる法律問題』というテーマで、近年のインターネット裁判実務の進歩についてコラムを寄稿いたしました。
編集部の許可を得て、一部再編集のうえ掲載したコラムを以下、再掲いたします。
インターネットをめぐる近時の法的課題
近時,インターネット(が急速に普及し日々新たなサービスが生み出されている。他方で,インターネットが社会の隅々まで浸透するにつれ,インターネットに起因する法的紛争も増加している。東京地裁保全部が担当したインターネット関連事件が,この4年で20倍の件数となったという報道も記憶に新しい。法律実務もインターネットの進歩を追従すべく,まさにドッグイヤーの様相で近時急速に進歩しており,新たな裁判例も急速に積み上げられている。
本稿では,インターネット上の情報発信に対する権利救済の分野について,近時の裁判例を取り上げつつインターネット法務全体を俯瞰したい。
渉外事件の増加
インターネット法務分野の近時の特徴として,外国法人が運営するウェブサービスが増加し,それに伴い権利救済のために運営者である外国法人を相手方として請求を行う事案が増えたことが挙げられる。報道されただけでもFC2,Inc,Twitter,Inc,Facebookに対する日本初の削除命令や情報開示命令が発令されている。
インターネット上の記事の削除については,不法行為に関する訴えであり不法行為地(被害結果発生地)として,被害者側の住所地に管轄がある。外国法人相手の場合であっても,国内の土地管轄が認められれば,我が国の国際裁判管轄も原則として認められている。他方で加害者特定のためのプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求は,不法行為に関する訴えには該当しない。そのため,我が国に営業所等を有しない外国法人の場合,国際裁判管轄が問題となる。外国法人の中には国際裁判管轄について争う姿勢を見せる法人もあるが,日本国内のユーザー向けに日本語によるサービスを提供している場合には,我が国に拠点を有していなくとも,我が国の国際裁判管轄を認めるのが実務上の運用となっている。
また,外国法人相手の裁判においては送達に長時間を要し,迅速性が求められる事案においては大きな問題となる。特に送達条約未加盟国等を相手とする場合は,仮処分手続であっても双方審尋期日までに数か月という期間を要する。裁判所も,高度に迅速性が求められる事案については無審尋による仮処分命令の発令を認めるなどをしているが,我が国の仮処分決定に任意に従わない相手にいかに対処するかなど,外国法人相手の裁判には手続上の問題は多い。
被害者側の手続的負担の増加
(日本国内に拠点を有しない)海外法人相手の裁判では、法律上の問題から削除請求と発信者情報開示請求の裁判管轄が分かれてしまい、それぞれ別々の裁判所で裁判を行わなければならないケースも増えている。これは、削除請求については被害者住所地に管轄が発生するが、発信者情報開示請求については民事訴訟規則により東京都千代田区に管轄が発生することによる。よって、東京23区外の被害者がこれらの裁判を行う場合、削除と発信者情報開示を別々の裁判所で行うことになる。
被害者側で事件を担当することが多い立場としては、例えば発信者情報開示命令が発令されたのちの削除請求に関しては発信者情報開示に関する裁判所の判断を尊重し柔軟な対応を期待したいが、プロバイダ側にも事情があり難しいところなのかもしれない。
Google,Inc.に対する検索結果削除命令
平成26年の大きなニュースとして,平成26年10月9日,東京地方裁判所は検索エンジンGoogleを運営する米国法人Google,Inc.に対し検索結果の削除を命じる仮処分命令を発令した事例が挙げられる。
これまでもGoogleに検索結果の削除を求める裁判は多数行われてきたが,裁判所の判断が示された事案ではいずれも棄却されており,他の検索エンジンも含め検索エンジンに対して検索結果の削除を命じた初の事例と思われる。なお,Google検索に関するこれまでの裁判の中には,Google日本法人を相手に申立を行った結果,削除権限は米国Google,Inc.にのみあるという理由で敗訴している事例が多数ある。東京地裁10月9日決定では,Google,Inc.を相手に申立がなされており,前述した渉外事件の増加の一つに位置付けられるであろう。
法理論的な面においては,EUデータ保護規則に言うところの「忘れられる権利」を,我が国においても認めた決定であるとも言われるが,この理解は不正確である。削除を認めた理屈としては人格権に基づく差止であり,従来の削除裁判と何ら変わるところはない。しかし,“従来と変わらない”ゆえに,本件事案は画期的かつ新しい裁判例と言える。
これまでの裁判では,「検索エンジンの公益性」と「自動的かつ機械的にサイトを収集しているだけで検索エンジンは内容に関知しない」という検索エンジン側の主張が重視され,人格権を違法に侵害する情報が検索エンジン上に存在しても,検索エンジンに故意過失が認められるような場合でなければ削除義務は認められないとされてきた。いわば,検索エンジンについては,他のコンテンツプロバイダとは異なる特権的な地位が認められていたのが従来の枠組みである。しかし,東京地裁10月9日決定では人格権を違法に侵害する情報が掲載されているのであれば,その検索エンジンを『管理する債務者に削除義務が発生するのは当然』と述べ,従来の特権的な地位を完全に否定した。検索エンジンも一般のコンテンツプロバイダと同様であるとした点が,本決定の画期的な部分である。
東京地裁10月9日決定では,検索結果上に表示されるページタイトルや抜粋部分に,実名とともにネガティブな内容が記載されている記事については削除が認められたものの,実名の表示がない記事等についてはリンク先に実名表記があっても削除は認められなかった。掲示板事案などではリンクによる人格権侵害を肯定する高裁判決も下されていることから,検索エンジンの削除義務がどの範囲まで認められるか,表現の自由とも関連し今後問題となると予想される。
なお,本命令後に下された大阪高裁平成27年2月18日判決(ヤフーに対する検索結果表示差止。昨年8月に一審京都地裁が請求を棄却した事件の控訴審)においても,検索結果の表示が違法性を有し検索エンジン運営者が削除義務を負うケースがあることが認められている。
新たな判断枠組み,基準の確立を
日々新たな問題がインターネット上で発生しており,裁判例の蓄積もなされているところである。しかし,裁判のよりどころとなる基準はノンフィクション『逆転』事件判決や,石に泳ぐ魚事件判決など,インターネットが爆発的に普及する以前のものであり,現在の状況に適用する基準としては不都合が生じるケースもある。インターネット時代に即した判断枠組みが確立されることが望まれる。
また,インターネット上の匿名の加害者を特定するための唯一の根拠法であるプロバイダ責任制限法は,新たなウェブサービスや通信方式の登場により,既に多くのケースにおいて実態にそぐわないものとなっている。趣旨解釈により法の文言の提供範囲を広げ被害者救済を図る裁判例も多数出始めているが,早急に抜本的な改正が必要である。
インターネットは我々の生活にとって非常に有益なツールであり,既に社会のインフラとなっている。インターネットから生じる権利侵害が,インターネットの活用を阻害する結果は避けなければならない。インターネットを社会のインフラとして適切に機能させるため,権利侵害を是正・救済する手段の確立が,我々法律家に今求められている。