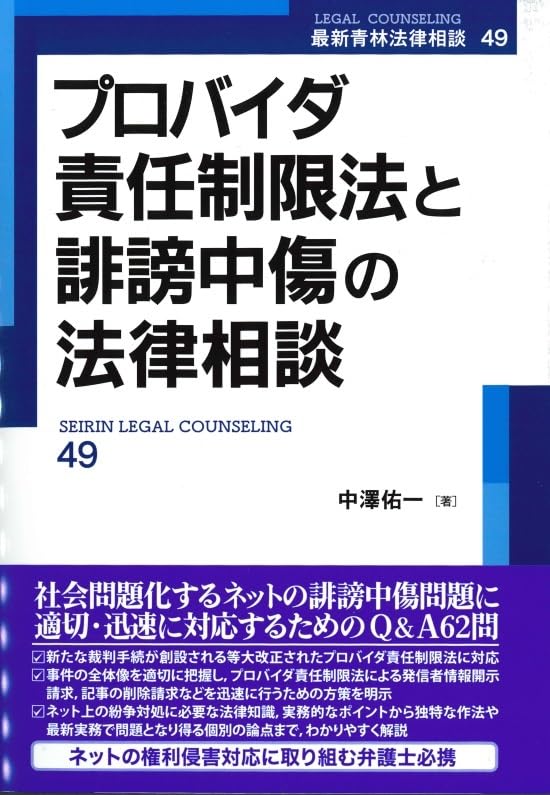弁護士 椿 良和
前回取り上げた事案と異なり、既に死亡している著名な実業家の名前やその肖像写真ないし画像を広告に利用する場合、どのような法的問題があるでしょうか。
[pullquote-left]1 パブリシティ権は相続されるか?[/pullquote-left]
最高裁平成24年2月2日第一小法廷判決(民集66巻2号89頁、以下「本件判例」といいます。)は、パブリシティ権が人格権に由来する権利として保障される旨判示しているところ、人格権とは、「各人の人格に本質的な生命、身体、健康、精神、自由、氏名、名誉、肖像および生活等に関する利益の総体」として認められています(芦部信喜・高橋和之補訂『憲法』[第七版]125頁(岩波書店、2019))。
このように、パブリシティ権を「人格権に由来する権利」、つまり、一身専属的な権利として構成した場合には、当該権利の帰属主体が亡くなることで当該権利は消滅し、当該権利の相続は認められないとも考えられます。
一方で、当該判例では、パブリシティ権は、「肖像等それ自体の商業的価値に基づくもの」であるとして、当該権利に財産的な価値を認めていることから、当該権利を財産権として構成した場合には、その相続が認められる可能性もあります。
そのため、パブリシティ権の相続性については争いがあるため、当該権利の権利者と主張する遺族との間で紛争になる可能性があります。
[pullquote-left]2 関連裁判例[/pullquote-left]
⑴ 東京地判平成26年2月12日損害賠償請求事件(平25年(ワ)7012号)
本件は、原告から書籍の制作を受託した被告が訴外Cの相続人の承諾を得ることなく書籍に訴外Cの写真を使用したなどとして、原告が被告に対し債務不履行に基づく損害賠償を求めた事案において、基本契約に基づく書籍の制作委託契約において、被告は、原告に対して他人の肖像権やパブリシティ権を侵害することのないよう注意すべき義務を負っており、他人の写真を使用する場合は許諾権者から許諾を得る義務を負っていたところ、訴外Cの相続人の許諾を得ることなく、書籍に訴外Cの写真を使用して、訴外Cの相続人が有するパブリシティ権を侵害するなどした被告には、書籍に係る製造委託契約上の債務不履行があるとして、書籍に係る制作委託契約上の債務不履行を認め、原告の請求を一部認容した事例です。
裁判所は、故人の写真の使用について、その相続人の同意を得なかった被告は、その相続人が有するパブリシティ権を侵害した旨認定しており、パブリシティ権が相続されたことを前提とした判断をしています。
⑵ 東京地判平成23年3月15日(平21年(ワ)34773号、契約不存在確認等請求事件)
本件は、歌手の妻であった原告が、本件歌手の所属していたプロダクションである被告に対し、本件歌手が被告との間で契約していたマネージメント契約が終了した後も被告において本件歌手の権利を無断で使用し、集金し、原告に損害を与えているなどと主張して、損害賠償請求をした事例です。
裁判所は、「原告は、Cの死亡によって、同人の有していた肖像権等の権利(本件権利)を遺産分割により相続し」たとして、肖像権が相続されることを認める判断をしています。
[pullquote-left]3 まとめ[/pullquote-left]
以上のとおり、関連裁判例では、パブリシティ権の相続を認めているものと思われるところ、広告利用のために無断で故人の肖像等を使用すると、当該故人の遺族と紛争になるおそれがあります。
そこで、紛争のリスクを回避するのであれば、当該故人の遺族から肖像等の使用につき同意を得るのが無難といえます。
ただし、故人が相当前に亡くなっているなど遺族が見つからない場合には、遺族から同意を得るのは難しいので、それでも故人の肖像等を利用する場合には、紛争のリスクがあることを考慮した上で、故人の名誉を害しない態様で肖像等を利用することになると思います。
なお、外国人のパブリシティ権侵害の場合(例えば、アップル社の共同設立者の一人であるスティーブ・ジョブズ氏の氏名や肖像)、準拠法について、日本法ではなく、当該人の国の法律も問題となりえます(通則法17条、19条、20条参照)。
また、肖像写真については、創作性が認められれば著作物となり、写真撮影者の著作権も問題となり得るところ、現行法では著作権は原則として著作者の死後70年間保護されますので注意が必要です。